TOP目次
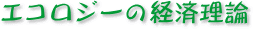
はしがき
環境問題の広がりと深刻化は,経済が物質的に閉じたシステムではないという事実を前提にした,新しい社会科学の展開を要求している。経済は,環境から物質を搾取し廃棄している開放システムである。この搾取と廃棄が環境に何の影響も与えないならば,仮想的に経済を閉じたシステムとして扱い,成長三昧の状況を望ましいと考えることは許されるかもしれない。しかし,身近な大気汚染や水質汚染から地球規模の諸問題まで,多様化し深刻化した今日の環境問題は,物質的閉鎖系としての経済という仮定を完全に非現実的なものとしてしまった。
20世紀の経済学は「均衡」という概念を一つの主要な軸にして発展してきた。経済学にとって均衡がこころよい響きをもった概念であるのは,それがシステムの「持続可能性」への期待と結びついているからである。財やサービス,それらの価値の流れが釣り合いのとれている状態であるか,一時的にははずれても均衡に向かう傾向が存在することによって,システムは持続的な存在の資格をもつと考えているのである。しかし,環境問題は,経済学的均衡の対象となるシステムの範囲の狭さをはっきりと示している。たとえ,経済というシステムの範囲では均衡が存在したとしても,それを支える環境との関係では均衡が存在していないのである。このような経済学にとって不愉快な状況を変えるために,直接問題となっている環境の部分を強引に経済に内部化する試みが行なわれてきた。経済と環境の接点を内部化するのである。たとえば環境が汚染されれば,汚染を引き起こす側あるいは汚染の浄化によって利益を受ける側に経済的負担を義務づける,などの政策の有効性を単純に否定することはできない。しかし,今日の環境問題には,環境が部分の寄せ集めではなく全体的で複雑なシステムとして劣化するという,新しい特徴があらわれているのである。
環境問題を考える上で最も重要な点は,「 環境もまた構造をもつ 」という認識である。環境はブラックボックスのようなものではない。環境は,物質循環と生態系という部分構造に分けることができる。物質循環とは,水と大気のグローバルな循環を主軸にした,すべての物質の流転であり,地球上の生物はこの循環の部分的な流れに関係することなしに存在できない。物質循環は人間も含めすべての生命を支えている大構造である。生態系とは多様な生物の物質的,非物質的な相互依存関係からなるシステムである。生態系はみずから構造を望ましい方向に変化させることができるという意味で,自己組織化能力をもっている。これらの部分構造の上に経済はみずからの構造を展開できているのである。したがって,このような環境の構造をできる限り正確に認識することによってはじめて,今日の環境問題を回避する正しい方向が明らかになる。
環境の構造とともに,環境に対する人間の側の関わり方を規定しているものとして,経済の構造そのものの正しい認識も必要になる。たとえば,今日の工業社会は,なぜあたかも物質的に閉じたシステムであるかのように,成長を追い求め続けるのか,これは鋭く重要な問いである。その問いに答えるためには,前工業社会との比較が必要になる。そしてそれは,結局,環境との持続的な共存が可能であるような社会はどのようなものであるべきかという問いにつながっていく。これらの問に答える上で, 経済的剰余という概念が重要な役割を果たす。剰余という概念は,余りものとか余計なものとかいう否定的な概念とみなされる一方,進歩への力の源泉であるという肯定的な評価も存在する。もともと人間は,生態系の冗長性としての剰余によって生かされ,経済はみずからが生み出す剰余によって進歩を遂げてきた。そして,この進歩が環境という外部制約によって行き詰まらざるをえない状況が生み出されてきているのが現代である。環境問題をシステムの問題と考える場合,剰余に動機づけられた社会そのものについての批判的分析が必要になる。重要なことは,このような剰余に対する批判は,環境問題を引き起こすシステムに対する批判であるとともに,富の追求のために人間全体を危険な賭けの担保にする社会のあり方そのものに対する批判につながっていくことである。
本書は,生態系と経済を貫く大構造としての物質循環という視点から,経済と自然環境およびそれらの間の相互関係に対する理解を深め,人類の持続的生存を可能にする新たな社会システムの見取り図を示すことを目的にしている。そして,今日の具体的な環境問題の解決の方向を定めるための新たな視点を提供し,環境が豊かであるとは何を意味するか,環境の価値とは何かなど,広く提起されている基本的な疑問にこたえるねらいももっている。
ところで,生態系のマクロ的あるいはミクロ的構造を理解する科学としてエコロジー(Ecology:生態学)がある。一方,経済を対象にして経済学が存在する。今日の環境問題が示している事実は,これら二つの科学の対象が実は一体不可分のものだということである。対象に対するこのような新しい認識に立脚した科学が必要になっている。本書は,環境としての生態系と経済を統一的な対象とする新しい科学の基本的枠組みを提示している。経済と生態系の統一性の客観的,認識論的な骨格である物質循環という視点を基礎にする科学を,本書では物質循環論と呼ぶことにする。
本書は,前著である『環境とエネルギーの経済分析』からの研究の発展の上に成立したものである。前著では,環境問題が人類のエネルギー利用の仕方の特殊性から発生しているという認識のもとに,人々の消費を維持するためのエネルギー利用の構造分析,またプラスチックリサイクルや太陽光発電といったエネルギー関連技術の評価を,産業連関分析と線形計画分析によって実証的に示した。これらの分析と評価のすべてを,経済が定常的に運行するという,成長志向から解放された状態にあることを前提としておこなった。このような経済のあり方を 定常循環系と呼んだ。そこにあるような,環境問題を解決するためにシステムの組織原理そのものの変更が求められているという視点は,そのまま本書にうけつがれている。また,環境問題の解決が定常的経済を基準にするという視点も変わっていない。ただ,前著では環境そのもの分析が不十分であった。私は,環境の構造の理解を前提にした議論の緊急性を,前著を書き終えた時点で痛感していた。本書はこのような問題意識による,その後の研究の今日の時点における集約である。
本書の,少なくとも第 1 章と第 6 章は読んでいただくことを期待している。第 1 章は本書の論理学にあたるもので考え方の枠組みを示している。特に物質循環とマクロ目的の相互関係を理解していただきたい。第 6 章は私の主張の基本的なものを含んでいる。人類史の一貫した理解における剰余概念の重要性と,自然と調和した社会の原理をとらえていただきたい。第 6 章では若干数式らしきものがでてくるが,ほんの初等的なものでしかない。数学的な議論をできる限り回避したまま,もう少し読む章を増やしてもよいという読者には,この二つの章の他に第 2 章,第 7 章,第 8 章を読まれることを期待している。第 2 章は,生態系について本書で必要な理解の最小限のものを記述することを目的にして書いている。その意味ではかなり重要な章である。第 7 章は第 6 章で提起した人類史理解の枠組みが日本近世社会においてどのように適用されるかを示している。第 8 章は人間と自然との調和を考える上で避けて通れない,現代社会における人間的欲求の問題の解明を意図している。さらに,ある程度の数学的議論にも耐えてみようと思われる読者,数学的議論そのものをとばしても主張を理解しようという読者は,第 3 章,第 4 章,第 5 章,第 9 章を是非読んでいただきたい。解説的な部分を読むだけでも,私の意図したところは十分理解していただけるものと確信している。終章は,物質循環論の哲学的側面を明らかにするための序章という意味で書き加えた。その内容を全面的に展開する研究も開始したいと考えている。また,付録として線形計画問題の双対定理に関する若干の説明を加えた。
本書では,巻末に掲げているように先人の少なくない著作を直接参照している。もちろん,私が本書をまとめるにあたって間接的に触発された文献は,私自身でも意識していないものも含め,これよりもはるかに多数である。一つ恐れることは,読者がここに掲げられている文献について,本書で参照している点のみが,私がそれらの文献を評価している部分であると錯覚されることである。それぞれの文献を本書で置き換えることはできないし,各文献が独自の豊かな内容をもっている。それぞれの著者に対して,私の引用や参照が失礼なものでないことを願っている。
本書は,多くの方々のさまざまな形の直接あるいは間接的な助力をえて,はじめまとめることができた。本書の第 1 章にふれられているカオス理論の理解について,柴山健伸氏(和歌山大学)には私の初歩的なたくさんの疑問にこたえていただいた。また,有賀裕二氏(中央大学)からは同理論の経済学への応用に関するいくつかの書を提供いただいた。第 2 章から第 5 章にかけては生態学的な内容で,基軸となる最大呼吸仮説は,1992年にストックホルムで開かれた国際生態経済学会 (International Society for Ecological Economics) の大会で初めて発表した。報告に対して,M.Giampietro氏(コーネル大学)から適切なコメントをいただき,その後も私の研究の展開方向について多くの助言をいただいた。また,龍谷大学理工学部の「瀬田セミナー」によって,長い期間にわたって生態学研究者の発表を直接きく機会をえることができた。1994年4月に京都で開催された「数理生物談話会」では,本書の第 4 章および第 5 章の基本的内容を発表したが,参加した方々から貴重なコメントをいただいた。第 5 章に用いられた線形モデルのターンパイク定理の理論的,実証的研究方法については,私が神戸大学大学院時代,当時,大阪大学におられた筑井甚吉教授(亜細亜大学)から1年間にわたって個人教授していただいたことが基礎になっている。またこの章は,1993年11月に開かれた環太平洋産業連関分析学会で報告され,久保庭眞彰氏(一橋大学)に討論者になっていただいた。第 6 章および第 9 章の基本的内容は,1994年3月に開かれた慶応大学経済学部環境プロジェクト主催の「環境コンファレンス」で発表された。この研究会代表幹事の細田衛士氏,寺出道雄氏をはじめ多くの参加者から有益な多数のコメントをいただいた。また,このコンファレンスを契機に,吉田文和氏(北海道大学)には,本書を構成することになる諸論文に目をとおしていただき助言をいただいた。第 7 章は,もともとは1988年2月に書いた,「穀物価値体系と封建制」という論文が出発点になっている。この論文は,神木哲男教授(神戸大学)の紹介で経済史関係の研究会で発表され,貴重なコメントを多くいただいた。また,西川俊作氏(慶応大学)からも内容の改善につながる助言をいただいた。第 8 章の一部は1988年の理論・計量経済学会での報告論文が基礎になっているが,その際,浅田統一郎氏(中央大学)に討論者になっていただいた。また,A.Robinson氏(オーストラリア国立大学林学部)には,日常的な電子メールの交換で,私の英語の論文に対して適切な改稿指示をいただき,海外のいくつかの学会における私の研究発表を激励していただいた。これらの私につながる研究者のネットワークの存在なしには,本書を完成させることは不可能であった。これらの方々および組織にあらためてお礼を申し上げる次第である。
また,和歌山大学経済学部におけるコンピュータおよびネットワークのすぐれた環境は,本書に結実する私の研究を促進する重要な契機となった。この環境の構築に努力されてきた床井浩平氏をはじめ同僚の諸氏に感謝申し上げたい。
最後に,本書の刊行を引き受けていただいた日本評論社お礼申し上げたい。また,同社編集部の守屋克美氏には,1993年のエントロピー学会での出会い以来,本書の出版を激励していただき,出版にいたる手続きを進めていただいた。研究者として,鋭敏な編集者との出会いの大切さを感じつつ,あらためて感謝申し上げる次第である。
1994年5月31日
鷲 田 豊 明
![]()