| 副目次 |
|
第 6 章 生態系の剰余から経済の剰余へ 1 節 生態系からの自立と剰余の発見 2 節 農耕の開始と剰余の自己目的化 3 節 農業社会の剰余と構造 4 節 農業社会から工業社会へ 5 節 労働社会という選択肢 6 節 剰余と環境危機 7 節 あらゆる形態の剰余を自然に返す |
| 副目次 |
|
第 6 章 生態系の剰余から経済の剰余へ 1 節 生態系からの自立と剰余の発見 2 節 農耕の開始と剰余の自己目的化 3 節 農業社会の剰余と構造 4 節 農業社会から工業社会へ 5 節 労働社会という選択肢 6 節 剰余と環境危機 7 節 あらゆる形態の剰余を自然に返す |
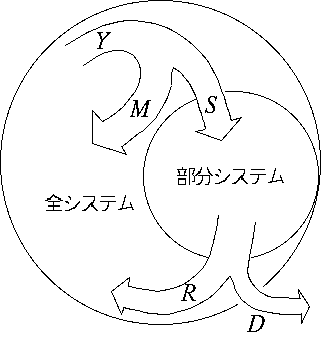
| 外部 | 植物 | 動物 | 分解者 | 剰余 | |
| 太陽光 | E | -Pg | |||
| 呼吸廃熱 | -R | Rp | Ra | Rd | |
| 二酸化炭素 | \pm C | \pm Cp | Ca | Cd | |
| 水 | W | -Wp | -Wa | -Wd | |
| 栄養塩類 | \pm N | -Np | Na | Nd | |
| 植物体 | \pm P | Pp | -Pa | -Ps | |
| 動物体 | \pm A | Aa | -As | ||
| 遺体・排泄物 | \pm D | Dp | Da | -Dd |
| 農業 | 工業 | 消費 | 生産 | ||
| 直接生産者 | 剰余から | ||||
| 水 | -W1 | W2 | W3 | W4 | -- |
| 栄養塩類 | -N2 | -- | -- | -- | -- |
| 植物体 | Ps | -- | -- | -- | -- |
| 動物体 | As | -- | -- | -- | -- |
| 遺体・排泄物 | -- | -- | D3 | D4 | -- |
| 土地 | G | -- | -- | -- | -- |
| 農業生産物 | X11 | X12 | C13 | C14 | Y1 |
| 工業生産物 | X21 | X22 | C23 | C24 | Y2 |
| 労働投入 | L1 | L2 | -- | -- | \bar{L} |
| 剰余 | S1 | S2 | S3 | -- | -- |
| 生産 | Y1 | Y2 | \bar{L} | -- | -- |

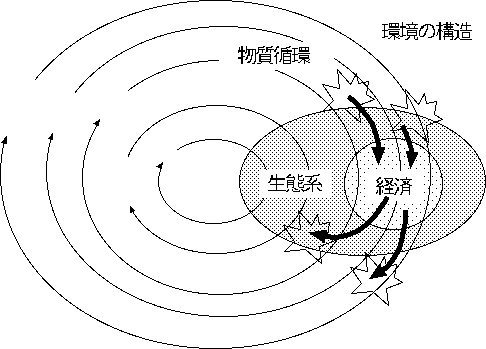
 。(もどる)
。(もどる) , 西田~
, 西田~ , p.38。(もどる)
, p.38。(もどる) にある小林達雄氏の諸論文。(もどる)
にある小林達雄氏の諸論文。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) , 中尾~
, 中尾~ , ヘンリ~
, ヘンリ~ , 鈴木~
, 鈴木~ 。(もどる)
。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) , 屋形~
, 屋形~ 。(もどる)
。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) , ウィットフォーゲル~
, ウィットフォーゲル~ , 川村~
, 川村~ , 関野~
, 関野~ , 安田~
, 安田~ 。(もどる)
。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) , p.74。「農業労働者はその労働が労働賃金以上に生産する唯一のものである。故にかれはすべての富*の唯一の源泉である」, チュルゴー~
, p.74。「農業労働者はその労働が労働賃金以上に生産する唯一のものである。故にかれはすべての富*の唯一の源泉である」, チュルゴー~ , p.27。この重農主義者のモデルに関する,労働価値の立場からの考察はマルクスによって与えられている。マルクス~
, p.27。この重農主義者のモデルに関する,労働価値の立場からの考察はマルクスによって与えられている。マルクス~ ルクス69}, pp.14,15,21。重農主義者の学説史的な位置づけについては三土~
ルクス69}, pp.14,15,21。重農主義者の学説史的な位置づけについては三土~ を参照。(もどる)
を参照。(もどる) , pp.483-484。(もどる)
, pp.483-484。(もどる) , 鷲田~
, 鷲田~ 。(もどる)
。(もどる) を参照。他に鷲田~
を参照。他に鷲田~ 。(もどる)
。(もどる) が参照されるべきである。他に鷲田~
が参照されるべきである。他に鷲田~ 。(もどる)
。(もどる) , 置塩~
, 置塩~ , 森嶋~
, 森嶋~ , Fujimori~
, Fujimori~ , Fujimori~
, Fujimori~ , Washida~
, Washida~ 。(もどる)
。(もどる) ルクス68}。また,剰余の人類史的意味に鋭い考察を加えた文章は,マルクス~
ルクス68}。また,剰余の人類史的意味に鋭い考察を加えた文章は,マルクス~ ルクス78} の「絶対的剰余価値ノート e 剰余労働の性格」, 同,pp.296-309, にみられる。このマルクスの剰余について深い考察を行ない,それを制度的変化の契機としてとらえる Pearson~
ルクス78} の「絶対的剰余価値ノート e 剰余労働の性格」, 同,pp.296-309, にみられる。このマルクスの剰余について深い考察を行ない,それを制度的変化の契機としてとらえる Pearson~ の主張は,ここでの剰余の定義との関連で注目されるべきである。他に寺出~
の主張は,ここでの剰余の定義との関連で注目されるべきである。他に寺出~ においてもマルクスの剰余概念の整理と分析がおこなわれている。(もどる)
においてもマルクスの剰余概念の整理と分析がおこなわれている。(もどる) の物質代謝論アプローチ*を参照。(もどる)
の物質代謝論アプローチ*を参照。(もどる) , 佐原~
, 佐原~ 。(もどる)
。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) がある。(もどる)
がある。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) , p.32。(もどる)
, p.32。(もどる) , p.219。(もどる)
, p.219。(もどる)