| 副目次 |
|
第 7 章 近世農業社会の剰余と編成原理 1 節 近世農業社会の基本問題 2 節 近世農業と物質循環 3 節 近世経済の二つのモデル 4 節 近世農業における技術選択の問題 5 節 米価値体系としての石高制 6 節 近世農業社会の不安定性と危機 |
| 副目次 |
|
第 7 章 近世農業社会の剰余と編成原理 1 節 近世農業社会の基本問題 2 節 近世農業と物質循環 3 節 近世経済の二つのモデル 4 節 近世農業における技術選択の問題 5 節 米価値体系としての石高制 6 節 近世農業社会の不安定性と危機 |
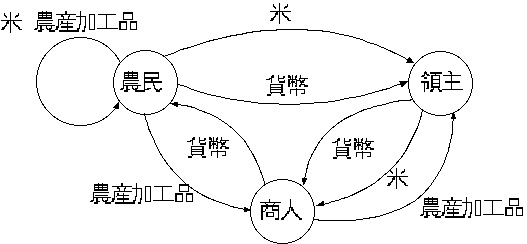
| 農業 | 商業 | 農民 | 商人 | 領主 | 生産 | |
| 米 | X1 | A1 | C1 | F1 | Y1 | |
| 農産加工品 | p2X2 | p2A2 | p2C2 | p2F2 | p2Y2 | |
| 商業サービス | p3F3 | p3Y3 | ||||
| 生産者所得 | M1 | M2 | ||||
| 年貢・賦課 | N1 | N2 | ||||
| 生産 | Y1+p2Y2 | p3Y3 |
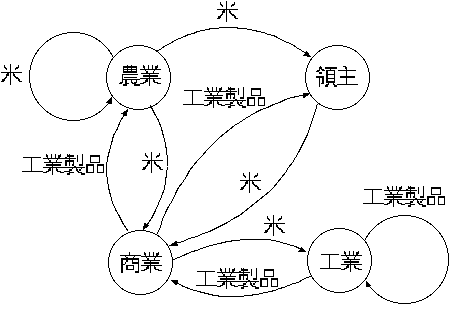
| 農業 | 工業 | 商業 | 農民 | 職人 | 商人 | 領主 | 生産 | |
| 米 | X11 | A1 | T1 | C1 | F1 | Y1 | ||
| 工業製品 | p2X21 | p2X22 | p2X23 | p2T2 | p2C2 | p2F2 | p2Y2 | |
| 商業サービス | p3X31 | p3F3 | p3Y3 | |||||
| 生産者所得 | M1 | M2 | M3 | |||||
| 年貢・賦課 | N1 | N2 | N3 | |||||
| 生産 | Y1 | p2Y2 | p3Y3 |
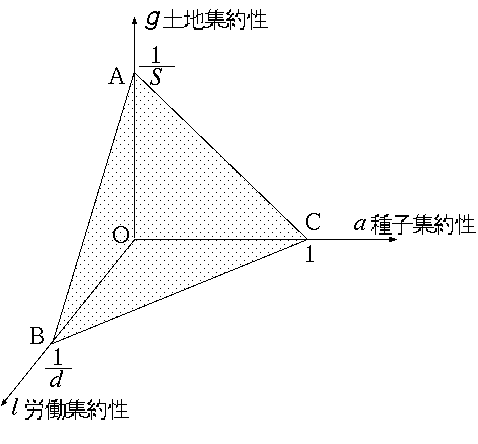
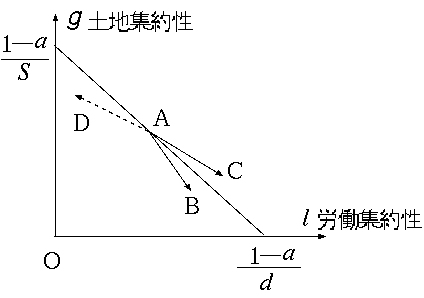
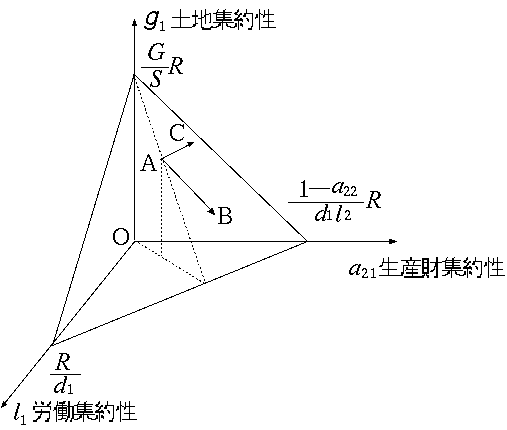
 , p.335よりとった。(もどる)
, p.335よりとった。(もどる) , p.344。(もどる)
, p.344。(もどる) , p.333より。(もどる)
, p.333より。(もどる) , p.227。(もどる)
, p.227。(もどる) , p.207(もどる)
, p.207(もどる) , p.75。(もどる)
, p.75。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) , p.185。(もどる)
, p.185。(もどる) , p.16。(もどる)
, p.16。(もどる) , p.208。(もどる)
, p.208。(もどる) , p.231。「小農経営が一般化する過程では,小農*の生産力発展はむしろ鍬の普及・発展にかかっていた」,古島~
, p.231。「小農経営が一般化する過程では,小農*の生産力発展はむしろ鍬の普及・発展にかかっていた」,古島~ , p.247。(もどる)
, p.247。(もどる) , p.73。(もどる)
, p.73。(もどる) , p.152。(もどる)
, p.152。(もどる) , p.129。他に飯田~
, p.129。他に飯田~ , 武井~
, 武井~ 。(もどる)
。(もどる) , p.47。(もどる)
, p.47。(もどる) , p.21。(もどる)
, p.21。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) , p.155。(もどる)
, p.155。(もどる) など。(もどる)
など。(もどる) , 第四章。(もどる)
, 第四章。(もどる) , p.14。(もどる)
, p.14。(もどる) , p.69。(もどる)
, p.69。(もどる) , p.191, 熊沢~
, p.191, 熊沢~ , p.334。また,中村孝也氏も米による価値体系が,交換経済の発展を抑圧し,武家階級の特権と地位を維持するためのものであることを鋭く指摘している。中村~
, p.334。また,中村孝也氏も米による価値体系が,交換経済の発展を抑圧し,武家階級の特権と地位を維持するためのものであることを鋭く指摘している。中村~ , p.245。(もどる)
, p.245。(もどる) , p.346。(もどる)
, p.346。(もどる) , p.130。(もどる)
, p.130。(もどる)