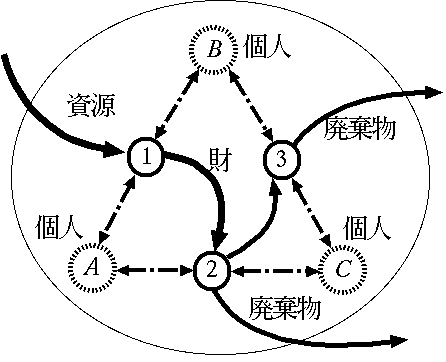
図(F1)モノに媒介された相互関係}
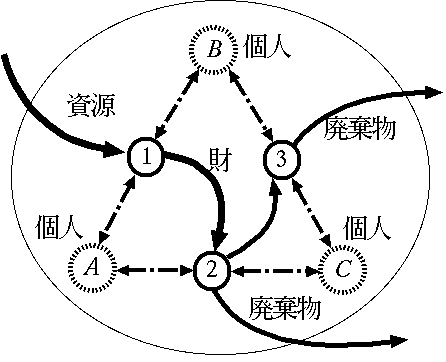
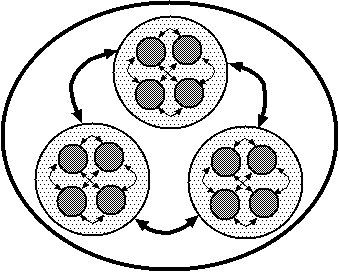
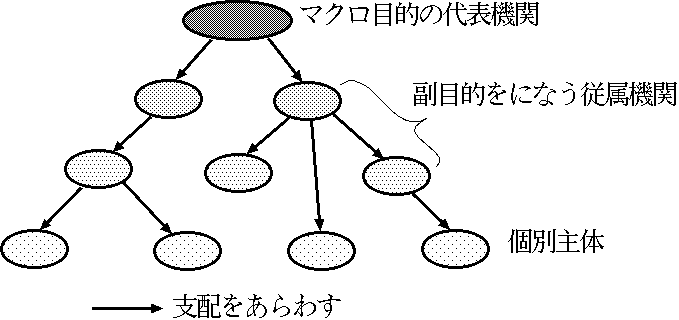
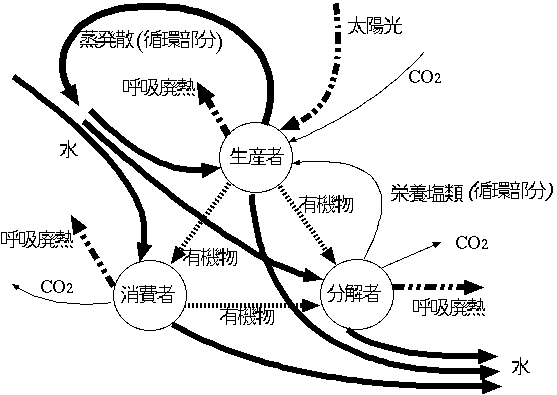
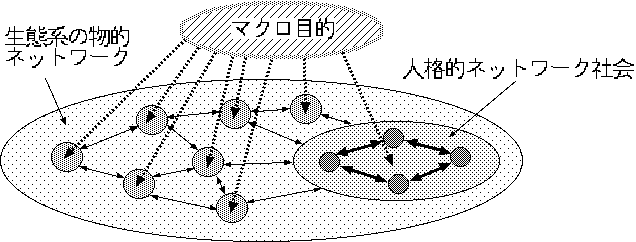
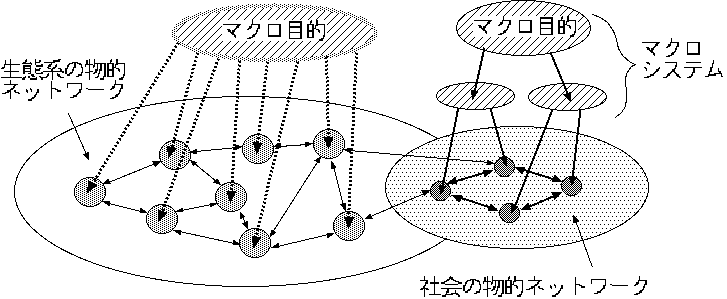
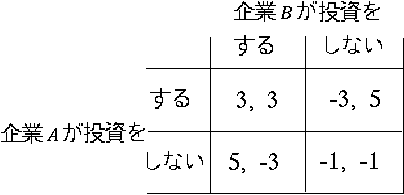
 ,p.34。公文俊平は「共通の文化をもつ主体群のあいだに、恒常的で定型的で規則的な相互行為(とりわけ相互制御)による結合関係が形成される結果、そこに一つの全体とみなすにふさわしい事物が成立しているという認識が,この関係を構成している主体に通有されるにいたっているとき,そのような全体のことを``社会システム"とよぶことにしよう」と述べている。公文~
,p.34。公文俊平は「共通の文化をもつ主体群のあいだに、恒常的で定型的で規則的な相互行為(とりわけ相互制御)による結合関係が形成される結果、そこに一つの全体とみなすにふさわしい事物が成立しているという認識が,この関係を構成している主体に通有されるにいたっているとき,そのような全体のことを``社会システム"とよぶことにしよう」と述べている。公文~ ,p.160。社会システムをどう定義するかは,分析目的に依存する側面を有するが,本書における立場は,全体性*をになう機構の相対的自立性の強調にあるといえる。システムについては,他に飯尾~
,p.160。社会システムをどう定義するかは,分析目的に依存する側面を有するが,本書における立場は,全体性*をになう機構の相対的自立性の強調にあるといえる。システムについては,他に飯尾~ ,村田~
,村田~ ,バックレイ~
,バックレイ~ など。(もどる)
など。(もどる) ,p.439。さらに次のようにも述べる。「自然の諸法則についての知識を商業と富をさらに伸長させる目的で利用することに私たちの主力を注ぎ込みつづけたならば,それを追い求めるのに熱心すぎたときに必然的にともなう悪が,手のほどこしようもないほどに巨大に膨れあがってしまうかもしれない」,同,p.440。この文明批判*は,交際があったといわれるJ.S.ミルとよく波長があっている。本書,第4章参照。(もどる)
,p.439。さらに次のようにも述べる。「自然の諸法則についての知識を商業と富をさらに伸長させる目的で利用することに私たちの主力を注ぎ込みつづけたならば,それを追い求めるのに熱心すぎたときに必然的にともなう悪が,手のほどこしようもないほどに巨大に膨れあがってしまうかもしれない」,同,p.440。この文明批判*は,交際があったといわれるJ.S.ミルとよく波長があっている。本書,第4章参照。(もどる) の第1章参照。(もどる)
の第1章参照。(もどる) ,pp.41-42 には水稲農耕を例にこれを示している。(もどる)
,pp.41-42 には水稲農耕を例にこれを示している。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) ,p.137。J.J.ルソーの「戦争*がおこるのは物と物との関係からであって,人と人との関係からではない」(ルソー~
,p.137。J.J.ルソーの「戦争*がおこるのは物と物との関係からであって,人と人との関係からではない」(ルソー~ ,p.23)と指摘しているのも,灌漑の制御をめぐる戦争*,交易ルートの確保*をめぐる戦争の両方にたいする洞察として鋭い。日本の場合も,戦争が発生したのは,物に媒介された社会である社会システムが形成されていった弥生時代以降なのである。本書,第5章参照。(もどる)
,p.23)と指摘しているのも,灌漑の制御をめぐる戦争*,交易ルートの確保*をめぐる戦争の両方にたいする洞察として鋭い。日本の場合も,戦争が発生したのは,物に媒介された社会である社会システムが形成されていった弥生時代以降なのである。本書,第5章参照。(もどる) においても一定の解明をおこなっている。(もどる)
においても一定の解明をおこなっている。(もどる) 。日本の場合は,弥生時代から古墳時代へかけての統一国家形成の動きは,水系単位の灌漑によって形成させられた社会が交易*という媒体によってそれを超えた秩序形成に向かう動きに対応している。 日本の場合は,灌漑という契機だけでは統一国家*には至らなかったのであり,それ以降,幕末*まで日本の農業社会全体を通して分権性が消えなかったのもこの社会システム形成の二段階性にあったとみることもできる。(もどる)
。日本の場合は,弥生時代から古墳時代へかけての統一国家形成の動きは,水系単位の灌漑によって形成させられた社会が交易*という媒体によってそれを超えた秩序形成に向かう動きに対応している。 日本の場合は,灌漑という契機だけでは統一国家*には至らなかったのであり,それ以降,幕末*まで日本の農業社会全体を通して分権性が消えなかったのもこの社会システム形成の二段階性にあったとみることもできる。(もどる) 。また,他にホイッタカー~
。また,他にホイッタカー~ ,太田他~
,太田他~ ,松本~
,松本~ ,宝月~
,宝月~ ,Begon et al.~
,Begon et al.~ など優れた参考書が数多くある。(もどる)
など優れた参考書が数多くある。(もどる) は,生態系概念における境界確定の困難性の問題を厳しく指摘している。しかし,森林生態系のなかに小さな土壌生態系が存在したりするなど,多様な生態系が包含関係にあったり,渡り鳥が遠く離れている生態系を分離しがたくしているなど,生態系どうしが関係づけられていたりすることは,この概念の弱点ではない。それは,システムの認識論的問題である。同じような問題は社会システムについても存在している。生態系や社会システムという全体的概念*を用いて現実の構造を認識する場合には認識する側の目的に現実の境界が条件づけられるのである。(もどる)
は,生態系概念における境界確定の困難性の問題を厳しく指摘している。しかし,森林生態系のなかに小さな土壌生態系が存在したりするなど,多様な生態系が包含関係にあったり,渡り鳥が遠く離れている生態系を分離しがたくしているなど,生態系どうしが関係づけられていたりすることは,この概念の弱点ではない。それは,システムの認識論的問題である。同じような問題は社会システムについても存在している。生態系や社会システムという全体的概念*を用いて現実の構造を認識する場合には認識する側の目的に現実の境界が条件づけられるのである。(もどる) ,小沢~
,小沢~ ,大串他~
,大串他~ など参照。(もどる)
など参照。(もどる) 参照。(もどる)
参照。(もどる) ,鷲田~
,鷲田~ 参照。このなかで私は,最大呼吸仮説が現実的なものであるならば,生態系全体の確実な持続のために自己の規模の拡大を「自発的に」抑止するというかたちで,特殊な利他主義*を発揮する個体群が存在する可能性が存在すると生態系のモデル分析の結果として指摘した。これにちょうど対応する実験的事実は栗原~
参照。このなかで私は,最大呼吸仮説が現実的なものであるならば,生態系全体の確実な持続のために自己の規模の拡大を「自発的に」抑止するというかたちで,特殊な利他主義*を発揮する個体群が存在する可能性が存在すると生態系のモデル分析の結果として指摘した。これにちょうど対応する実験的事実は栗原~ のなかで報告されている。すなわち,フラスコのなかの実験的生態系において,原生動物がバクテリアを食べ尽くさないように,原生動物自身がそれを抑止するための物質をだすことがわかったのである。同書,pp.180-181 参照。この生態系から明らかになったシステム一般の問題については,本書の補論を参照。(もどる)
のなかで報告されている。すなわち,フラスコのなかの実験的生態系において,原生動物がバクテリアを食べ尽くさないように,原生動物自身がそれを抑止するための物質をだすことがわかったのである。同書,pp.180-181 参照。この生態系から明らかになったシステム一般の問題については,本書の補論を参照。(もどる) ,第7章参照。(もどる)
,第7章参照。(もどる) 参照。(もどる)
参照。(もどる)
 を参照されたい。(もどる)
を参照されたい。(もどる)
 参照。(もどる)
参照。(もどる)