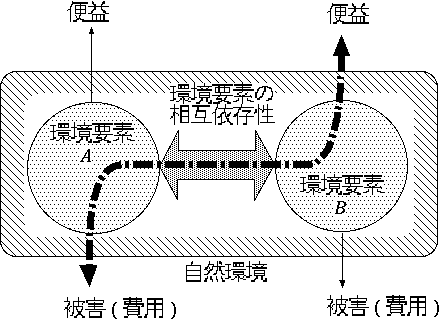
図(F1) 環境要素の相互関係と環境問題
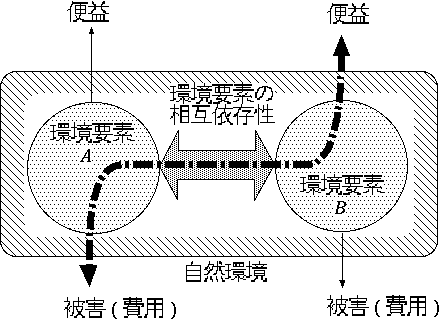
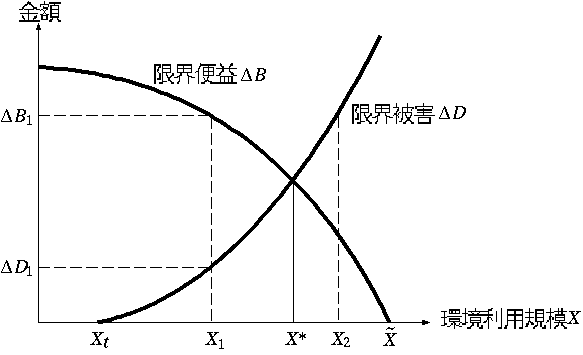
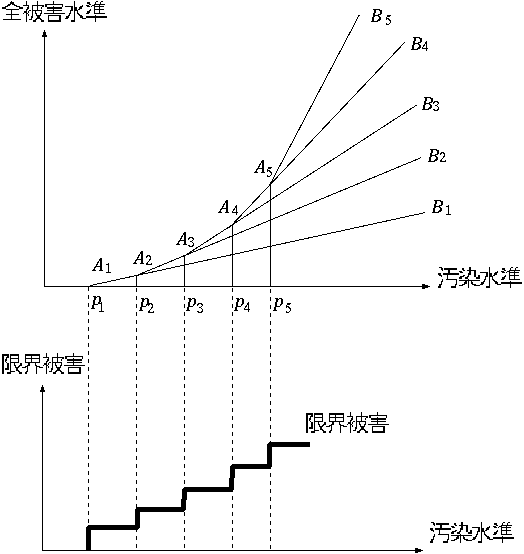
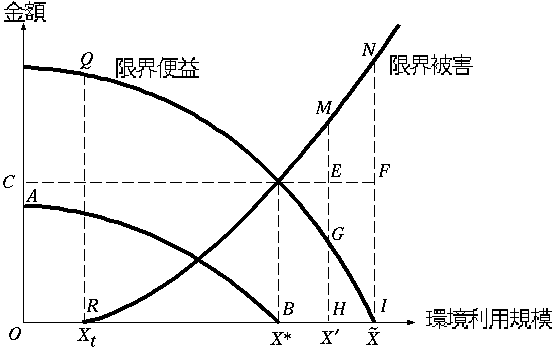
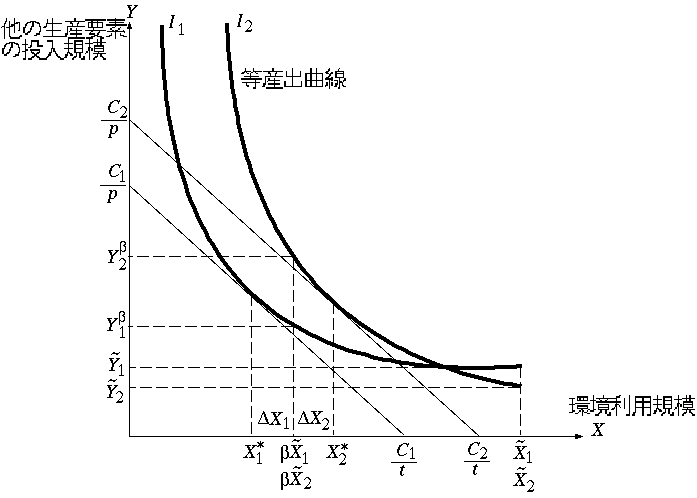
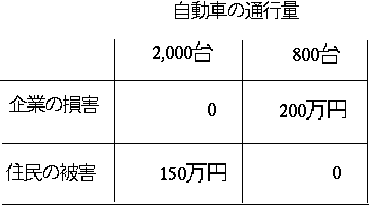
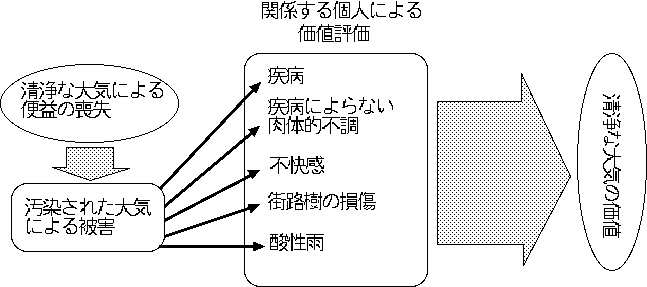
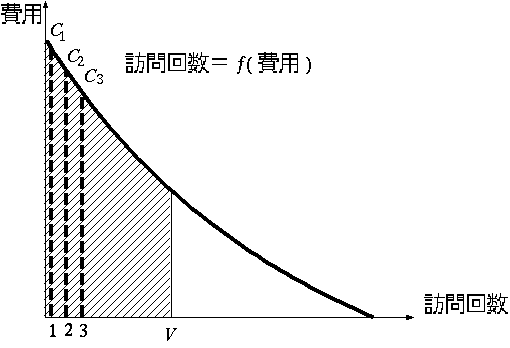
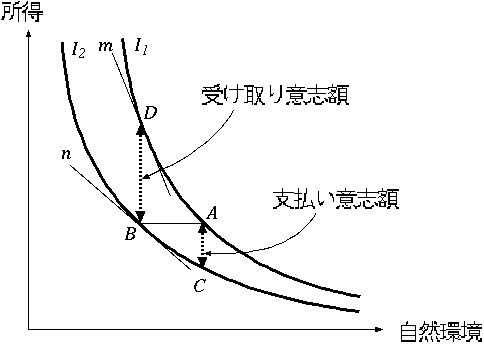
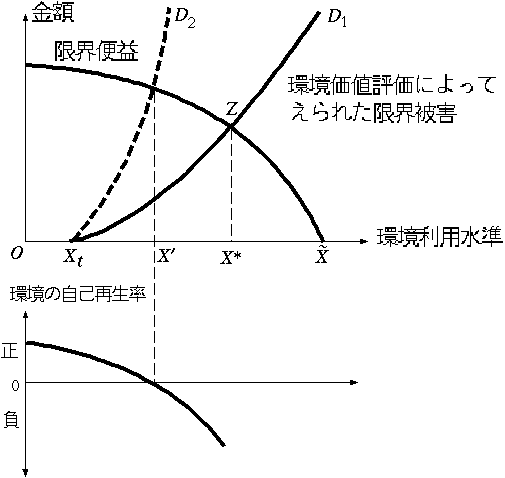
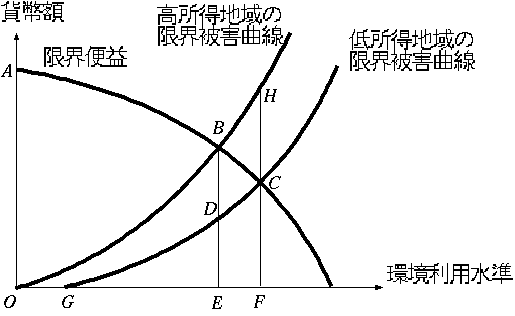

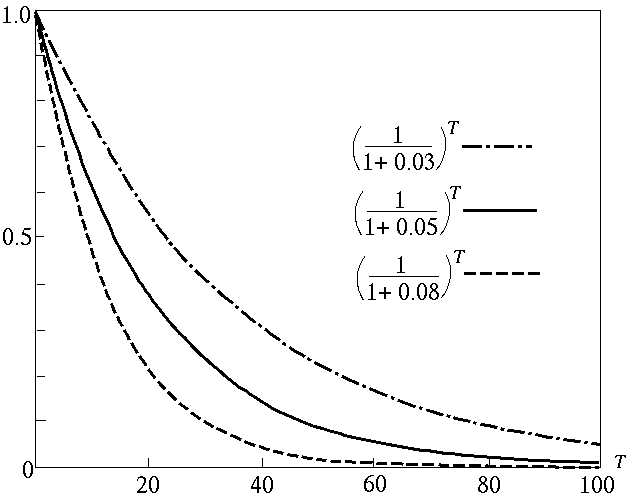

 参照。(もどる)
参照。(もどる) の Chapter 14 を参照。(もどる)
の Chapter 14 を参照。(もどる) に依拠している。(もどる)
に依拠している。(もどる) において示された。ただし,この論文の中心的な主張は,ピグー税が前提としているような被害をだす側の責任をつねに問題にするというのではなく,与えられた状況を全面的に考慮しながら結論をだす必要性である。コースの定理はその前提となるものとして与えられているのである。他に,コース~
において示された。ただし,この論文の中心的な主張は,ピグー税が前提としているような被害をだす側の責任をつねに問題にするというのではなく,与えられた状況を全面的に考慮しながら結論をだす必要性である。コースの定理はその前提となるものとして与えられているのである。他に,コース~ も参照。(もどる)
も参照。(もどる) ,数学的に精密な議論と事例とを織り混ぜた教科書として岸本~
,数学的に精密な議論と事例とを織り混ぜた教科書として岸本~ などがある。 (もどる)
などがある。 (もどる) がある。また,環境の価値評価にかんする理論と実証をまとめた好著として Hanley and Spash~
がある。また,環境の価値評価にかんする理論と実証をまとめた好著として Hanley and Spash~ がある。 仮想市場法の具体的手順についてはこの著書への依存度は高い。他の価値評価方法についてもこの著書と,その他に,Pearce~
がある。 仮想市場法の具体的手順についてはこの著書への依存度は高い。他の価値評価方法についてもこの著書と,その他に,Pearce~ , ピアス, マーカンジャ, バービア~
, ピアス, マーカンジャ, バービア~ ,末石~
,末石~ ,Turner, Pearce, and Bateman~
,Turner, Pearce, and Bateman~ など参照。(もどる)
など参照。(もどる) ,柴田~
,柴田~ など参照。このような戦略的バイアスの影響が大きくないことを示した実証例としては,Bohm~
など参照。このような戦略的バイアスの影響が大きくないことを示した実証例としては,Bohm~ 。(もどる)
。(もどる) 参照。(もどる)
参照。(もどる) など適当なミクロ経済学のテキストを参照。(もどる)
など適当なミクロ経済学のテキストを参照。(もどる) は,対象になっている公共財の他の財への代替効果*が小さい場合に支払い意志額と受け取り意志額の大きな差異があらわれることを示した。また,この点にかんする実証的研究としては,Shogren et al.~
は,対象になっている公共財の他の財への代替効果*が小さい場合に支払い意志額と受け取り意志額の大きな差異があらわれることを示した。また,この点にかんする実証的研究としては,Shogren et al.~ などがある。(もどる)
などがある。(もどる) がある。(もどる)
がある。(もどる) では非利用価値の内容についての理論的分類と実証結果が示されている。理論的分類は,ピアス~
では非利用価値の内容についての理論的分類と実証結果が示されている。理論的分類は,ピアス~ , Pearce~
, Pearce~ なども参照。 (もどる)
なども参照。 (もどる) , p.66 参照。 (もどる)
, p.66 参照。 (もどる) は存在価値の大きさを示すとともに,仮想市場法によるこの種の価値評価が不安定で環境政策の基礎としてはふさわしくないと指摘する。 (もどる)
は存在価値の大きさを示すとともに,仮想市場法によるこの種の価値評価が不安定で環境政策の基礎としてはふさわしくないと指摘する。 (もどる) は仮想市場法によって価値を決定することが市場による価値の決定を決定することとはまったく異なっていると指摘する。前者は個人による社会的な選択であり,後者において個人は個人的な決定しかおこなっていないというわけである。(もどる)
は仮想市場法によって価値を決定することが市場による価値の決定を決定することとはまったく異なっていると指摘する。前者は個人による社会的な選択であり,後者において個人は個人的な決定しかおこなっていないというわけである。(もどる) は「包含効果」*と呼び,このような規模の差異の評価にかかわる問題の他に,より包括的な財の一部として聞かれた場合と単独で聞かれた場合の価値がちがってくるという問題についてもこれに含めて議論している。(もどる)
は「包含効果」*と呼び,このような規模の差異の評価にかかわる問題の他に,より包括的な財の一部として聞かれた場合と単独で聞かれた場合の価値がちがってくるという問題についてもこれに含めて議論している。(もどる) による。この評価については Arrow~
による。この評価については Arrow~ など参照。また,Carson~
など参照。また,Carson~ はDevousgesらの結果について,跳び値を刈り込むことで規模と評価価値の正の相関がでてくる可能性を示している。(もどる)
はDevousgesらの結果について,跳び値を刈り込むことで規模と評価価値の正の相関がでてくる可能性を示している。(もどる) は仮想市場法による価値評価が経済的選好にもとづく価値評価ではなく,公共的意見の投票であり,環境破壊などによる経済的被害の価値評価には適用すべきでないと結論し,環境の保護のためには経済的評価ではなく,政治的規制の方が有効であると述べている。 (もどる)
は仮想市場法による価値評価が経済的選好にもとづく価値評価ではなく,公共的意見の投票であり,環境破壊などによる経済的被害の価値評価には適用すべきでないと結論し,環境の保護のためには経済的評価ではなく,政治的規制の方が有効であると述べている。 (もどる) および Spash~
および Spash~ でおこなわれている。(もどる)
でおこなわれている。(もどる)
 はある湿地生態系*の価値を商業価値,リクリエーションの価値*,気象被害を緩和する価値などから計測し,もう一方でその生態系の植物による1次生産を石油換算した価値から計測して比較分析した。生態系の1次生産能力をその価値としたことは注目に値する。しかし,それを経済的価値に転換しなおすのでは,結局,ここで指摘した価値均衡論の問題を避けることができなくなる。(もどる)
はある湿地生態系*の価値を商業価値,リクリエーションの価値*,気象被害を緩和する価値などから計測し,もう一方でその生態系の植物による1次生産を石油換算した価値から計測して比較分析した。生態系の1次生産能力をその価値としたことは注目に値する。しかし,それを経済的価値に転換しなおすのでは,結局,ここで指摘した価値均衡論の問題を避けることができなくなる。(もどる) ,p.139 を参照。(もどる)
,p.139 を参照。(もどる) ,Pearce and Turner~
,Pearce and Turner~ などに詳しい。(もどる)
などに詳しい。(もどる) で詳細に分析している。 他に鷲田~
で詳細に分析している。 他に鷲田~ も参照されたい。 (もどる)
も参照されたい。 (もどる)