| 選好順位 |
住民構成比 |
x |
y |
z |
| x > y > z |
(35%) |
105 |
70 |
35 |
| y > x > z |
(10%) |
20 |
30 |
10 |
| y > z > x |
(22%) |
22 |
66 |
44 |
| z > y > x |
(33%) |
33 |
66 |
99 |
| 計 |
(600%) |
180 |
232 |
188 |
表(T1)順位投票によるポイントの集計
第三列以降は,各選好態度を示すグループについて,各選択肢の順位のポイントにそのグループの構成比をあらわすパーセントをかけたものである。したがって,全ポイントの合計は600ポイントとなる。これをみると,少し驚かされるが,放置(y)のポイントが最も高くなり,第二位は環境改善(z),そして第三位にようやく工場進出(x)がくるのである。この結果は,最初の各個人の第一位順位だけを投票する一人一票の投票とはまったく逆の結果になってしまった。
つまり,全体として工場進出より環境改善を望む人が多いという批判から,第一位順位の投票結果を守るために各個人がもっている順位の重要性を強調するためにそれをより徹底し順位投票をおこなうと,結果がまた逆になってしまったのである。
しかし,この個人の選好の順位にしたがってなんらかの重みをつけることには無視できない問題がある。全体として,工場進出と環境改善を比べれば,環境改善をより選好する人の方が多い。それにたいして,環境改善を一位にあげる人と二位にあげる人を集計において同列に扱うことの反批判があったのであるが,これは実は人々の選好の強さが比較できるものだという前提に立っているのである。つまり, y > z > x という選好順序で z > x である人と z > y > x という選好順序において z > x である人とでは後者の方が環境改善にたいする選好が強いという前提に立っているのである。かりに,個人間である対象にたいする選好の強さが比較できるという前提に立ってみよう。すると奇妙なことが起こる。
いま,前者の選好順序に立つ個人 A と後者の選好順序に立つ個人 B の二人がいて,図~F1 のような選好強度がとらえられたとしよう。
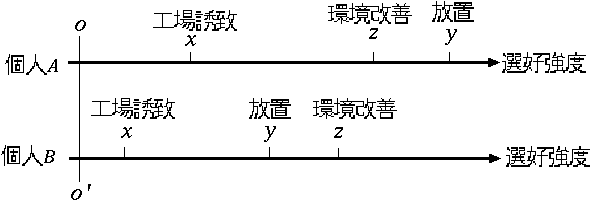
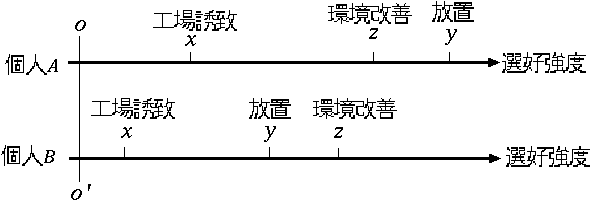
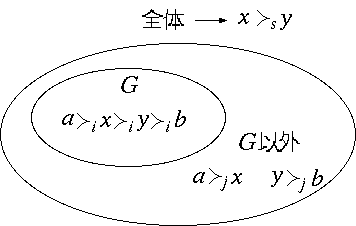
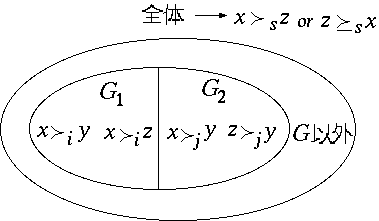
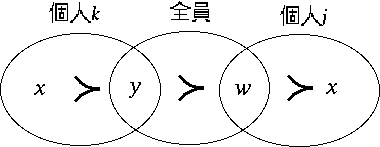
 ,p.24,補助定理1の(c)および(f),あるいは Sen~
,p.24,補助定理1の(c)および(f),あるいは Sen~ ,p.10,Lemma 1*a. を参照されたい。(もどる)
,p.10,Lemma 1*a. を参照されたい。(もどる) ,Sen~
,Sen~ 参照。(もどる)
参照。(もどる) および Sen~
および Sen~ をもとにしている。アローの不可能性定理についての議論は他に アロー~
をもとにしている。アローの不可能性定理についての議論は他に アロー~ ,Sen~
,Sen~ ,村上~
,村上~ ,ライカー~
,ライカー~ ,鈴村~
,鈴村~ などを参照。(もどる)
などを参照。(もどる) ,セン~
,セン~ ,鈴村~
,鈴村~ ,長久~
,長久~ を参照。(もどる)
を参照。(もどる) にあるものに依存している。(もどる)
にあるものに依存している。(もどる) , p.258。(もどる)
, p.258。(もどる)