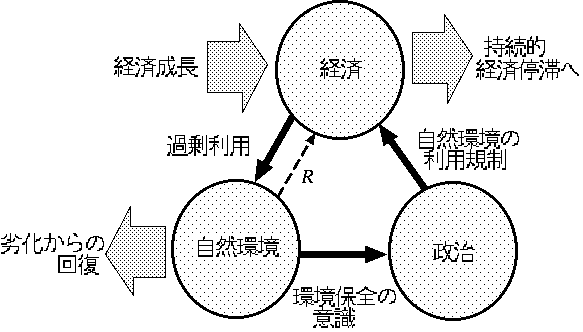
図(F1) 持続的経済停滞をめぐる因果関係
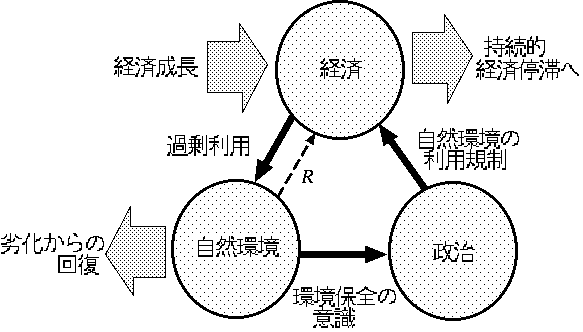
 ,p.266。また次のようにも指摘している。 「その地味や気候の性質,ならびに他の国々にたいするその位置がゆるすかぎりで,富の全量をあますところなく獲得した国,したがってまた,これ以上前進も後退もできない国では,労働の賃金も資本の利潤もおそらくは極めて低いであろう」,同,p.281。 (もどる)
,p.266。また次のようにも指摘している。 「その地味や気候の性質,ならびに他の国々にたいするその位置がゆるすかぎりで,富の全量をあますところなく獲得した国,したがってまた,これ以上前進も後退もできない国では,労働の賃金も資本の利潤もおそらくは極めて低いであろう」,同,p.281。 (もどる) ,第8章を参照。(もどる)
,第8章を参照。(もどる) ,p.141。(もどる)
,p.141。(もどる) 参照。同書は,次のマルクスの理論を理解するうえでも参考になる。(もどる)
参照。同書は,次のマルクスの理論を理解するうえでも参考になる。(もどる) ルクス1968},第三篇「利潤率の傾向的低下の法則」参照。(もどる)
ルクス1968},第三篇「利潤率の傾向的低下の法則」参照。(もどる)
 参照。(もどる)
参照。(もどる) 参照。(もどる)
参照。(もどる) ,p.31。(もどる)
,p.31。(もどる) の第4章2の「長期停滞に関する諸見解」を参照。(もどる)
の第4章2の「長期停滞に関する諸見解」を参照。(もどる) ,p.108。(もどる)
,p.108。(もどる) ,p.107。(もどる)
,p.107。(もどる) あるいは鷲田~
あるいは鷲田~ など,あるいは適当な経済学のテキストにあたるとよい。(もどる)
など,あるいは適当な経済学のテキストにあたるとよい。(もどる) ,p.161。animal spirits を「血気」としたのは邦訳にしたがった。ケインズがこのパラグラフで書いている次の文章も示唆的である。「企業が将来の利益の正確な計算を基礎とするものでないことは,南極探検の場合とほとんど変わりがない。したがって,もし血気が鈍り,自生的な楽観が挫け,数学的期待値*以外にわれわれの頼るべきものがなくなれば,企業は衰え,死滅するであろう。ただし,その場合,損失への恐怖は,さきに利潤への希望がもっていた以上に合理的な基礎をもっているわけではない」,ケインズ~
,p.161。animal spirits を「血気」としたのは邦訳にしたがった。ケインズがこのパラグラフで書いている次の文章も示唆的である。「企業が将来の利益の正確な計算を基礎とするものでないことは,南極探検の場合とほとんど変わりがない。したがって,もし血気が鈍り,自生的な楽観が挫け,数学的期待値*以外にわれわれの頼るべきものがなくなれば,企業は衰え,死滅するであろう。ただし,その場合,損失への恐怖は,さきに利潤への希望がもっていた以上に合理的な基礎をもっているわけではない」,ケインズ~ ,p.160。(もどる)
,p.160。(もどる) ,p.137。(もどる)
,p.137。(もどる) ,p.139。「民主主義を無制限な多数決原則と乱暴に同一視するのを拒絶することにはしっかりした根拠がある。「人民」を単に人民の多数派と同一視するのも不可能ならば,「人民による統治」を多数者による統治と同一視するのも,ましてや多数者の代表による統治と同一視するのも不可能なのである」,アーブラスター~
,p.139。「民主主義を無制限な多数決原則と乱暴に同一視するのを拒絶することにはしっかりした根拠がある。「人民」を単に人民の多数派と同一視するのも不可能ならば,「人民による統治」を多数者による統治と同一視するのも,ましてや多数者の代表による統治と同一視するのも不可能なのである」,アーブラスター~ ,p.106。(もどる)
,p.106。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) ,アーブラスター~
,アーブラスター~ など参照。(もどる)
など参照。(もどる) ,p.33。(もどる)
,p.33。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) ,p.31.(もどる)
,p.31.(もどる) ,p.90。(もどる)
,p.90。(もどる) ,p.30。(もどる)
,p.30。(もどる) 。(もどる)
。(もどる) ,p.404。(もどる)
,p.404。(もどる) ,p.430。(もどる)
,p.430。(もどる) クファーソン1978},p.130。また,シュムペーター理論が内在させているこのような経済行為とのアナロジーについては,ダウンズ~
クファーソン1978},p.130。また,シュムペーター理論が内在させているこのような経済行為とのアナロジーについては,ダウンズ~ によって新古典派経済学的な解釈がおこなわれた。(もどる)
によって新古典派経済学的な解釈がおこなわれた。(もどる) ,p.147。(もどる)
,p.147。(もどる) ,p.94。ここでルソーの民主主義というのは,ルソーが述べている政治理念全体をさすものと考えていただきたい。(もどる)
,p.94。ここでルソーの民主主義というのは,ルソーが述べている政治理念全体をさすものと考えていただきたい。(もどる) クファーソン1978},p.168。(もどる)
クファーソン1978},p.168。(もどる) ,p.131。(もどる)
,p.131。(もどる) ,p.132。(もどる)
,p.132。(もどる) ,p.133。(もどる)
,p.133。(もどる) に詳しい。(もどる)
に詳しい。(もどる) ,p.203。ルソーもまた,「抽籤による選挙は,真の民主制のもとでは,ほとんど不都合を生じないであろう」と述べている(ルソー~
,p.203。ルソーもまた,「抽籤による選挙は,真の民主制のもとでは,ほとんど不都合を生じないであろう」と述べている(ルソー~ ,p.153)。(もどる)
,p.153)。(もどる) ,p.286。この他まだいくつかの条件を述べている。(もどる)
,p.286。この他まだいくつかの条件を述べている。(もどる) ,その他については,河村~
,その他については,河村~ に詳しい。(もどる)
に詳しい。(もどる) など参照。(もどる)
など参照。(もどる) ,p.290)。しかしその理由はルソーと同じではない。(もどる)
,p.290)。しかしその理由はルソーと同じではない。(もどる) ,p.73。(もどる)
,p.73。(もどる) ,pp.289-294。(もどる)
,pp.289-294。(もどる) ,p.311。(もどる)
,p.311。(もどる) ,p.126。(もどる)
,p.126。(もどる) ,p.128。(もどる)
,p.128。(もどる) ,p.293。(もどる)
,p.293。(もどる) がある。このような,参加型の民主主義論は,マクファーソンの場合もそうだが,個人の意識の高まり,自発性の強化などにより大きく期待するものとなっている。(もどる)
がある。このような,参加型の民主主義論は,マクファーソンの場合もそうだが,個人の意識の高まり,自発性の強化などにより大きく期待するものとなっている。(もどる) ,p.123 以降。(もどる)
,p.123 以降。(もどる) ,p.127。(もどる)
,p.127。(もどる) ,p.125。あるいは,「小事に自由を使用することを知っていない大衆が,どうして大事に自由を用いることができようか」,トクヴィル~
,p.125。あるいは,「小事に自由を使用することを知っていない大衆が,どうして大事に自由を用いることができようか」,トクヴィル~ ,p.190,と鋭く指摘している。(もどる)
,p.190,と鋭く指摘している。(もどる) ,p.45。(もどる)
,p.45。(もどる) 。(もどる)
。(もどる)